どうも、ダイチです。
今年は人生史上最も本を読んだ一年でした。
育児の合間を縫って、読みに読んだ本、本、本。
本の山!
振り返りの意味も含めて、その本たちを一年の終わりにランキングにしとこうと思います。
面白い、ためになる、感動する、そんな本たちを厳選してみました。
全部素晴らしい本。
もしよかったらどれか読んでみてください。
Contents
2018 心に残った本 ベスト20
1位 ホモ・デウス
ジャンル:文化人類学
一位はこれ。
いろんなサイトや書店でおススメされていて、これを一位にもってくるなんて芸がないんやけど、それも仕方ない。
大ヒットとなった『ホモ・サピエンス』の続編みたいな感じ。
もちろん、前作を読んでいなくても大丈夫。
『ホモ・サピエンス』が人類の過去を解き明かした本なら、こちらは未来。
疫病、貧困、戦争を克服した人類はどこへ向かうのか・・・
人間の神へのアップデート、を合言葉にこれからの人類の在り方を大胆に予想していく。
AIと遺伝子工学がやはり肝、な感じ。
AIと合体し、あるいはスーパー遺伝子を受け継いだ、人間の姿をした神が実体として現れたとき、世の中はどうなるか。
とにかく面白い。好奇心センサーがピーン!
読みやすく、ためになる。
世の中には2種類の人間がいる。
これを読んだ人間か、読んでいない人間である。
2位 夜と霧
ジャンル:ノンフィクション・歴史・戦争
アウシュヴィッツ収容所を奇跡的に生きて出たユダヤ人医師の記録。
新版と旧版があり、旧版にはアウシュヴィッツはじめ各収容所の実態を記した解説と写真がついている。
内容は言語を絶する。
この本に限っては、多くのことを語れない。
人間の尊厳が全て奪われた地獄で、人は何を思い、感じ、生きるのか。
魂が震えるような感動と、救いようのない絶望が交互に押し寄せる。
この本を読み終わって自分の人生をかえりみたとき、絶対に言えることは、苦しみとの向き合い方が変わる、ということ。
これほどまで影響力を持った本を僕は知らない。
言葉の言い回しなどがやや難解で、中高生にはちょっと厳しいかも、というレベル。
旧版をおススメします。
3位 ユング心理学入門
ジャンル:心理学
1967年に刊行されて以来、心理学の入門におけるバイブル的存在となった一冊。
古臭さも時代遅れ感もなく、普遍的な内容。
本格的に心理学を学ぶ人は必ずどこかで出会う本。
ユングのはじめた分析心理学は、いわば無意識という最も不可思議かつパワフルな領域へのアクセスを試みるもの。
無意識を理解することは、全ての心理学流派にとって土台となる基礎知識。
心理学的教養の結晶のような本。
ただ、少し長く、読むのには根気がいる。
4位 困難な成熟
ジャンル:エッセイ
我が心の師匠、内田樹先生の本。
教育のこと、政治のこと、経済のこと、労働のこと、いろんな分野の本質を教えてくれる。
全部が根っこの話。表面上の話はない。
知の巨人による易しい生き方講座みたいなもの。
成熟とは、仲介者の役割を担うこと。
成熟した人とは、折り合わないものを折り合わせることに、知性的・感性的な努力を集中させられる人のこと。
この本を読んだ後は、なんかちょっと大人の男になった気分がするから不思議。
5位 人はなぜ「死ぬのが怖い」のか
ジャンル:科学・哲学
「死」を科学的に考えまくった本。
博学が過ぎる著者が本気で死ぬことは怖くない、と思うようになった理由を一から解説してくれる。
「死」を取り扱っているのだが、取り扱うものが大きすぎて、さまざまな分野へと論は飛び火し展開されていく。
進化、意識、感情、ロボット、宗教、哲学、神、禅、などなど、、、
好奇心をそそる知識のごった煮みたいな本。
例えば、進化。
死が怖い、ということを進化論的に考えてみた場合、それが存在する理由は次のいずれかである。
1、死の恐怖があるから、人は環境に適応できる
2、死の恐怖は、進化によって獲得した他の性質からもたらされた仕方のない「おまけ」である
3、死の恐怖は、我々の進化前の生物のなごりである
こういう検証がずっと繰り返される。
でも、飽きない、不思議と。
ちなみに、読んだからといって死ぬことが怖くなくなるというものではない。
6位 生物と無生物のあいだ
ジャンル:生物学
生き物ってどう定義されるの?
ということに答えてくれる本。
雑学本かと思いきや、100%がそうではなくて(そういうところもあるけど)。
生物学の研究史、と言ったほうが適切だと思う。
研究者たちは何を求め、どう研究し、どう失敗し、何を成し遂げてきたのか。
それを軸にして、生き物の本質を明らかにしていく。
驚きなのは、研究の厳しさ!!
自分は人文学系だったので、理系の研究者たちのシビアさには言葉がなかった。
彼らの苦労、気迫、ひらめき、そして、情熱。
そういう人間ドラマと生命の奇跡がマッチしてさわやかな感動が訪れる。
小説のようなテイストも感じられて、とても良い。
7位 7つの習慣
ジャンル:自己啓発
今更僕などが言うことなど何もない名著中の名著。
全てはアマゾンのレビューが物語っている。
読んだのが2018年とは、遅すぎたことを後悔しているレベル。
自己啓発というものを毛嫌いして読まない!という選択肢は愚か(笑)
人生の原則にすえるべき7つの習慣が紹介される。
僕は勝手に「人格の整形手術のノウハウ本」と言っている。
8位 バウッダ
ジャンル:仏教
「バウッダ」とは聞きなれないが、ブッダのこと。
仏教をちゃんと知りたいならこれで間違いない、という本。
絶対に間違いない。
なぜなら、筆者の中村氏と三枝氏は仏教研究の神様みたいな人だから。(ブッダに神様ってなんか渋滞気味やな)
仏教の基礎基本を徹底的に教えてくれる。
仏教の起こり、変遷、思想、各用語の解説、日本仏教の真実、全部をカバー。
書店なんかでよく見る『1時間でわかる!仏教入門』みたいなのとは根の深さが違う感じ。
ただ、仏教という広大な範囲を研究者視点で丁寧に慎重に解説しているので、入門書だけれど、難解かつ重厚。
1時間では第一章も読めないかもしれない・・・(笑)
9位 日本の歴史1 神話から歴史へ
ジャンル:日本史
初版は1965年。
時の試練を乗り越え、今なお燦然と輝く不朽の歴史書。
中央公論『日本の歴史』シリーズ!!!
全27巻あるうち、9位はこれ。第一巻。
イザナギ、イザナミ、アマテラスにスサノオ。
日本書記と古事記、そしてその原本となった書物を参考に日本神話をくわしくおさらい。
これが、めちゃくちゃ面白い。
ほんとにおもしろい。
そのあとは、実在したと確定できる天皇を推定し、物語である神話から事実である歴史へと流れていく。
歴史の研究を追うのってミステリに似てる。
筆者は長年、学校歴史教科書の責任者であった井上氏。
日本人として知っておくべき知識満載。
全国のお寺や神社へ行くのが楽しみになる。
ただ、研究色が強く、ある程度の根気と情熱が必要。
10位 神々の山嶺
ジャンル:山岳小説
ここへきて初めての小説。
実際に存在した登山者たちをモデルにした作品。
登山好きなら読むたび山へ行きたくなること請け合い。
登山の描写は圧巻の一言。
自分の息まで白く凍り、肺が痛い、と錯覚するほど。
さらに、山によって人生を救われた者、狂わされた者、山と人生が一体になっている者たちが織り成す人間ドラマが華を添える。
人生を懸けた人間でさえ、山の前ではちっぽけだ。
だが、そのちっぽけさに、ちっぽけさゆえに、壮大なドラマがうまれる。
浄化作用がある小説。
11位 クリスマス・キャロル
ジャンル:小説
めっちゃほっこりするディケンズの小説。
英語の勉強のため簡易版を読んだが、あまりに素晴らしく日本語訳を再読した。
やつれて意地汚い心しかもたない主人公に起こるクリスマスの奇跡。
現実にはあり得ない奇跡なのに、なぜかリアリティが半端ない。
さすが、名作といわれるものはちがうなぁ、と変に感動した。
今を大切に生きよう、周りの人を愛して生きよう、って思わされる。
すぐに読める。
学生にオススメしたい一冊。
12位 狂いのすすめ
ジャンル:哲学・自己啓発
無茶苦茶刺激的な本。
「お前らみんな強い者のふりをした雑魚だ」
「弱者は自分のことを弱者と認めて人生が始まる」
「今の世の中狂ってるんだから、お前さんもお狂いなさい、ちょっと狂ってて正常だ」
「常識や世間体は強者が弱者を縛るための鎖なんだよ」
とまぁ、終始こういうスタンス。
それがはまれば、本当に面白く感じられる。
僕はめっっちゃはまった。
この考え方は危険やし、怖いもんやと思う。人を成功者と敗者に分別し、”敗因”を努力不足に集約する。運命のサイコロを完全に無視し、全ての成功者にふんぞり返ることを許容するエゴイスティックな宗教。
強者にしか許されない宗教であり、弱者は断固受け入れてはならない宗教。 https://t.co/rJGUAo1V41
— ダイチ (@0Save) 2018年12月12日
しましまぁ、世の中の大半の人間は、自分のことを弱者だとは思っていない。
強者ではないが、少なくとも強者予備軍であると勘違いし、強者の理論に賛同する。
その行為がまさに強者によって計算され、真の強者の栄養になっていることを知らない。
雑魚は幻想を抱かされ、強者の栄養となる。
— ダイチ (@0Save) 2018年12月12日
だからもう、自分のことを弱者だと決めていればいいのにな。自分は成功者でないし、大した才能もない。歴史に名を残したり、月に行くようなことは間違ってもない。でも、自分が喰い物にされる思想の片棒を担いだりはしない。せめて、強者の理論の反対を行く。世間の常識に抗う。
— ダイチ (@0Save) 2018年12月12日
この通り影響されまくり。
たくさんの人に読んでほしいと思う一冊。
13位 魂にメスはいらない
ジャンル:対談エッセイ
『ユング心理学入門』の河合隼雄氏と大詩人谷川俊太郎氏の対談エッセイ。
谷川俊太郎が生徒、河合隼雄が先生として話が進む。
知の巨人の共演にファンは胸アツ。
著者の名前だけで期待値MAX
ユングの心理学を紐解きつつ、心理学と文学の交差点をめぐる。
目玉は、谷川の詩を河合が心理学的観点から解説をするところ。
恐縮しつつも、圧巻の解釈はさすが心理学界屈指の文筆家の面目躍如。
ユングに興味がある人はもちろん、谷川ファンも大満足間違いなしの一冊。
14位 革命のファンファーレ
ジャンル:マーケティング・自己啓発
非常に話題となった西野さんの本。
ジャンル分けが非常に難しいが、自己啓発というよりは新時代のマーケティング本と言えると思う。
経営戦略にも触れているし、生き方のヒントのようなものもちりばめられている。
大筋は、「煙突街のプペル」という絵本をいかにして大ヒットさせたかの詳しい解説である。
これが、ことごとく常識をぶっ壊した新たな手法で、痛快である。
今まさに目の前に迫った資本主義の進化系、評価主義経済での常識を身に付けられること請け合い。
レイアウトや文字サイズが工夫されていて読みやすさ抜群。
#革命のファンファーレ とすると高確率で本人がリツイートしてくれるんだとか。
著者の先見の明と、類まれなるセンスにしびれてしまう一冊。
15位 謎の独立国家ソマリランドそして海賊国家プントランドと戦国南部ソマリア
ジャンル:紀行文
世界で最も危険な地域の一つソマリア。
リアル北斗の拳、という不名誉な名で呼ばれる。
しかし、実はその内部に平和な“自称”民主主義国家が存在していた!?
暴力の吹き荒れる国において、銃を放棄し民主主義の形を整えたソマリランド。
辺境マニア、こと高野氏はその秘密をさぐるべくアフリカの角へと飛んだ。
笑って、勉強できるレアな社会派紀行文。
アマゾンレビューがその質の高さを物語る。
500ページを超える大作、長期休みにどっぷりはまってみてはいかが?
16位 日本の歴史2 古代国家の成立
ジャンル:日本史
日本の歴史シリーズ第二巻。
主に、飛鳥時代を取り上げる。
聖徳太子、蘇我馬子、藤原鎌足、天智天皇、天武天皇ら有名人が登場。
大化の改新、壬申の乱、などの詳細を追っていくが、これがもうほとんど小説のよう。
章のタイトルも、「クーデター前夜」などという具合。
皇室の血みどろの跡取り問題や複雑すぎる血縁・婚姻関係は読んでいてくらくらする。
壮大な人間ドラマを観ているうちに歴史通になれるという稀有な本。
ただし、これもまた第一巻と同様に難解かつ重厚な一冊ではある。
17位 煙を吐かぬ煙突
『煙を吐かぬ煙突』 (リンク先は青空文庫)
ジャンル:怪奇小説
夢野久作の短編小説。
彼の作品は、上品なグロテスクさが魅力。
残酷さの中にキラキラ光る幻想的な世界観が混ざり込んでいる。
定期的に読みたくさせる中毒性の高い作品を数多く残している。
この作品もその一つ。
背筋がゾクっとするけどおすすめ。
20分ほどで読める。
夢野久作といえば、『ドグラマグラ』だが、はじめて読む彼の作品としては、おすすめできない。
18位 人工知能は人間を超えるか ディープラーニングの先にあるもの
ジャンル:人工知能
人工知能って結局何なの?
今現在何ができるの?
これからどうなりそうなの?
なんでこんなに話題になってるの?
ということに丁寧に答えてくれる本。
これからの時代を生きていく人間は読まなければならない(断定)
絶対読んだ方がいい。
僕は『ホモ・デウス』に影響されてこの本の重要性に気が付いた。
人工知能の4つのレベルは、各方面で常識となりつつある概念。
本当に早めに読んだ方がいいとしか言えない。
3年前の本だけど、人工知能の基礎基本を教える本はこれがまだ最善みたい。
ここでもアマゾンのレビューが全てを物語る。
19位 カウンセリングの実際
ジャンル:心理学・カウンセリング
心理学界の重鎮、河合氏のカウンセリングハウツー本。
ハウツーと言ってもパターン化されたわかりやすいものではない。
氏の実際の経験談をもとに、カウンセリングをおこなう者が備えるべき心構えが粛々と記されている。
カウンセリングの難しさ、苦労、必要とされる覚悟がどしどし伝わる本。
人と人のやり取りの深淵さ複雑さにため息が出る。
本格的に心理学に興味が出てきたり、カウンセリングについて学びたい人でないと正直キツイかも。
20位 死と身体 コミュニケーションの磁場
ジャンル:エッセイ
我が心の師匠、内田樹先生の本。
レヴィナス研究と合気道とをライフワークにしている著者。
その経験から導かれる「死」と「身体」の原則。
生きる上で、常に心掛けておきたいアイデアでいっぱい。
例えば、
頭は命が無限だと勘違いしている身体を信じよ。
緊急の時、決断の時こそ身体的センサーを最大化せよ。
わからないことをわからないまま結論付けずに我慢しておけるのが本当の知性
こんな感じ。
一生ついていきます。師匠。
以上、20位まで紹介しました。
本はいいねぇ、本当に。
2019年も読書を楽しもうっと。
では、また。
本もいいけど動画もどうですか?⇒絶対ためになるTEDプレゼン動画
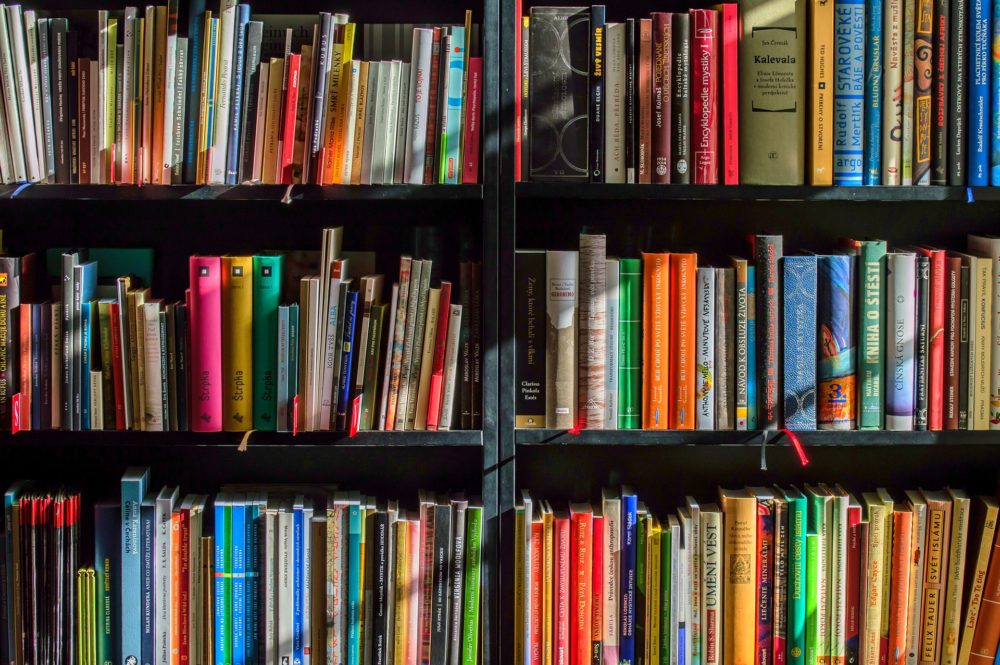























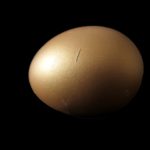





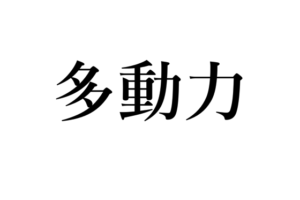


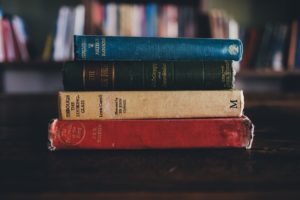
コメントを残す