先日、「習慣の本質」について書きました。
なぜ、あなた(僕も含め)の習慣は長続きしないのか?という内容です。
結論を言うと、
・結果から逆算して習慣を作ろうとするとほぼ失敗する
・習慣とアイデンティティはセットで育てろ
・習慣は最適化の前にまず標準化せよ
・強度より頻度を重要視せよ
というお話でした。
参照記事はこちら⇒⇒Atomic Habitsに学ぶ「習慣の本質」 あなたの習慣が続かないたった2つの理由
今日はこれの続きです。
もっと具体的に習慣の育て方、行動の定着のさせ方を紹介します。
元ネタはこの本。

ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣
とんでもなく濃い内容なので、僕の方で特に重要そうなものだけ取り上げます。
Contents
How to 習慣の正しい作り方
メソッド1 はっきりさせる
何をやるか、どこでやるか、いつやるか、どれくらいやるかをあらかじめ決定させておきます。
例えば、筋トレを例に挙げると、
①腕立て伏せを
②リビングで
③月・水・金の午後6時に
④20回する
という感じです。
習慣の内容は、はっきりしているほど良いそうです。
人は本能的に楽をしたい、今までの生活に変化を起こしたくない生物です。
ですから、はっきり決めていないと、悪い方へブレます。
例えば、「毎日筋トレをする」ということしか決めていなかったら、どうでしょう。
何の種目をするか、どこで、いつするか、何回するか、というような未決定事項が多くなります。
未決定事項が多いということは、言い訳するチャンスがそれだけ増えるということです。
さらに言えば、「決定する」という負荷が余計にかかってしまいます。
筋トレ+意思決定 がタスクになってしまうわけで、意思決定の分、余計にエネルギーを消費してしまいます。
※決めたことは紙に書いておくとより効果的です。
メソッド1 「習慣の内容をできる限りはっきりさせよう」
メソッド2 今ある習慣でフリをつける
行動は初動にもっともエネルギーを要します。
車のエンジンと同じです。
行動の習慣化にとってその問題を超えることは極めて重要です。
メソッド2の提案は、今ある習慣に新たな習慣をくっつけるということです。
例えば、
・朝コーヒーを飲む習慣に1分の瞑想習慣をくっつける
・仕事から帰って仕事着を脱ぎ、洗濯機に入れる習慣に筋トレをくっつける
といった具合です。
こうすると、新しい習慣の存在を忘れにくくなります。
そして、前習慣の「フリ」がついて新しい習慣に入りやすくなります。
物理的、精神的にすでに「動き」がついているので、次の動きへ移りやすいんです。
さらにもう一つ効果があって、それは、前習慣が「快」を感じるものだと、その続きにある新しい習慣も「快」を感じやすくなるのです。
コーヒーを飲むのが、「快」ならば、セットになった瞑想も「快」だと脳は判断します。
仕事着を脱ぐのが「快」ならば、セットになった筋トレも「快」だと脳は判断します。
是非取り入れた方が良い習慣の作り方だと思います。
メソッド2 「今ある習慣に新しい習慣をくっつけよう」
メソッド3 事前準備をする
行動の初動を助けるためにもう一つ方法があります。
それは、事前準備をする、です。
例えば、
・仕事帰りに筋トレをするなら仕事へ行く前に、ダンベルとタオルを出しておく
・毎朝生ジュースを飲むなら、寝る前にジューサーとコップを出しておく
・毎晩読書をするなら、あらかじめ本を枕の上に置いておく
などです。
これには行動の初動を助ける大きな効果があります。
またそれと同時に、この事前準備もれっきとした習慣の一部としてアイデンティティの形成に役立ちます。
これにより習慣の定着がよりスピーディーに進むことになります。
アイデンティティの形成と習慣の関係が分からない人は以下の記事をお読みください。
Atomic Habitsに学ぶ「習慣の本質」 あなたの習慣が続かないたった2つの理由
メソッド3 「事前準備をしよう」
メソッド4 2分間だけやる

習慣を育てる順番は、標準化(定着)⇒最適化でした。
そこで、はじめのうちは習慣は「定着」させることが最重要になります。
そこで、「2分だけやる」を提案します。
一回の習慣にかかる負担を極限まで減らします。
2分だけできれば合格、とするのです。
習慣の定着にとって大事なのは、強度よりも頻度です。
頻度が増えるにしたがい、アイデンティティが強固に形成されていきます。
そのためには、その行動が「頻度を高めることのできる軽い強度であること」が本当に重要なのです。
習慣が定着すれば、いくらでも強度を上げることができます。
まずは、2分間を目安としましょう。
メソッド4 「最初のうちは2分間だけやろう」
メソッド5 カレンダーで頻度を評価する
習慣による成果は、はじめのうちは捨てましょう。
結果にどれだけ近づいたか、で習慣を評価すると、まずうまくいきません。
頻度を評価しましょう。
それも目に見える形で。
おすすめは、カレンダーへのチェックです。
これだけやった、という形が「自分はこれをやる人間である」というアイデンティティを強めます。
それをやるのが当たり前、となった時が習慣の標準化の終わるタイミングです。
すなわち、頻度による評価を終えるタイミングです。
それまでは、「とにかくたくさんやっている」「そういう人間に変化している」ということをモチベーションにしましょう。
メソッド5 「目に見える形で習慣の頻度を評価しよう」
おわりに
今日は、基本的な5つのメソッドを紹介しました。
これを基本として習慣を作ってみるとたぶん、何も知らずに始めるよりかなりうまくいくはずです。
もし、もっとくわしくこれらの内容について知りたければ、是非以下の本を参照ください。
では!

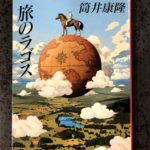





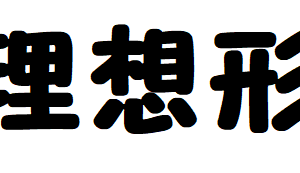



コメントを残す