どうも、ダイチです。お久しぶりです。約3か月ぶりにPCの前に座ります。
ブログより面白いものを見つけてしまいガッツリのめり込んでました。
いやほんと面白過ぎです。英語と心理学(カウンセリング)の勉強。
でもすこし目標へ近づいた感じがあるので、これからはバランスを取ってブログも書いていこうと思います。
Contents
カウンセリングって何だよ
しばらく心理学をテーマにしたいと思います。
はい、今日はこれ。カウンセリングについて。
最近、カウンセラーってどこにでもいますよね。
学校にはスクールカウンセラー。企業には産業カウンセラー。街には美容カウンセラー。病院にも保健所にも役所にも、もちろんカウンセラー。いたるところにカウンセラー。
心理学がいわゆる自然科学として認められ、日本に輸入されて約120年。
希少な存在だったカウンセラーの数は毎年最高数を更新し続けています。
時代のニーズというやつですかね。
でもね、そんなにポピュラーになったカウンセリングなんですけども、次のバカみたいな単純な質問に答えられる人は人口の3%もいないでしょう。
question
カウンセリングって何をするの?その目的は何なの?
わかったらすごいと思います。
正解はすぐ後に書きます。
ちなみに、「悩みを相談する」「アドバイスを受ける」「診断される」などは全てブッブーです。
カウンセリングの正体
では一体カウンセリングとは何なのでしょう。
※ちなみにこの二人、野球で言ったら王貞治とイチロー、相撲で言ったら白鳳と朝青龍って感じで超スーパーな心理学者さんです。
カウンセリングの前提
カウンセリングの前提には次のものが挙げられます。
- カウンセラーとクライアントがともに力を合わせる協力体制が必要なこと
- カウンセラーが治すのでもクライアントが治るのでもなく、二人でともに困難に向かうこと
- 面接時間や場所はカウンセラーが取り決めること
- カウンセリング以外の場では基本的に接点を持たないこと
- カウンセラー、クライアントともに拒否権を持っていること
ここでわかるのは、カウンセリングは一般的な「治療」ではないということですね。
そう、カウンセラーは医者ではないのです。
治すのでも治るのでもなく、その中間、二人でよくなっていく。
これがカウンセリングの知られざる大前提です。
カウンセラーは、監督やコーチではなく伴走者のようなイメージですね。
カウンセリングの真の目的
ここであえて、「真の」目的にしたのは、理由があります。
それは、クライアントとカウンセラーの目的は、いつの場合も若干食い違っているからです。
あれ、おかしいですよね。
さっき、「二人で困難に立ち向かうことこそカウンセリングの本質だ」みたいなことを言ったくせに!
なのに目的がずれているって何なのでしょう?
クライアントの目的は一つです。
今ある外的な(目に見える、あるいははっきりと存在が確認できる)障害を取り除きたい、それのみです。
当たり前ですよね。
不登校、手の震え、対人恐怖症、赤面恐怖症、ノイローゼ、過食、などなど。
こういうのを無くしたい!と思っているわけです。
これがカウンセリングを受ける目的です。
さて、一方カウンセラー側。
カウンセラーはこう考えます。
クライアントの外的な障害は、クライアントの内的な成長が果たされることで取り除かれる、と。
はい、今さらっとすごいこと言いました。
ここにカウンセリングの最大の肝があります。
そもそも心理学は、長い間科学として認められませんでした。
哲学や神学などと同じ人文系の学問だったわけです。
しかし、その「心の学問」を「心理学」という近代自然科学にエントリーさせた男がいるのです。
名をフロイトといいます。
彼は、人間の無意識に注目しました。
そして、無意識の領域は、絶えず我々の思考や感情、行動、あるいは身体状況にまで影響を与えていることを証明したのです。
今や人間の無意識が身体を含むあらゆるものに影響を及ぼすことは、心理学を少しでもかじった人なら常識として知っています。
この「無意識」という概念を得、はじめて心理学の歴史は科学とともにスタートを切ったのです。
カウンセラーにとって、クライアントの外的な障害は、無意識からの警告でありSOSです。
意識上の自分を自我と呼びますが、自我だけでは対処しきれない、またはずっと意識に留めておくにはつらすぎる心的外傷は、全て無意識に抑圧されます。
その抑圧された心的外傷は、無意識の中で肥大していきます。
そして、外部の特定の現象に反応し、何らかの障害を引き起こすのです。
わかりやすく例えれば、幼少期イジメを経験した人は、大勢の人が集う場所に行くと対人恐怖症が出る可能性があります。
それは、抑圧されたイジメの記憶が原因にあると考えるのです。
こんなにわかりやすい例はないかもしれませんが、理屈ではそういうことです。
自分では意識できない無意識の領域にこびりついている心的な「何か」が外部の現象に刺激されて症状として現れる、これが基本メカニズムです。
話を戻します。
ですから、カウンセラーは、外部に出てくる症状を外部の力によって解決することを第一の目的とはしていません。
どういうことかというと、例えば、不登校の子どもがいたとします。
その場合、カウンセラーの真の目的は、その子の学校での嫌なことを取り除いてあげることではありません。
その子の無意識にどんな心的事柄がこびりついているのか、そして、それが何によって刺激され、なぜ不登校という形で現れるのかを突き止めることです。
さらに、その子が無意識の領域に抑圧した心的事柄を自我に統合し、さらなる人格の成熟を果たせるように協力することです。
症状を無くすには、外的なサポートが必要なことがもちろんあります。
というか、実際には多いのですが、あくまでもカウンセラーの真の目的は、クライアントの内的な成長です。
内的な成長とは、つまり、何らかの事情で無意識に留めてある心的事柄を、意識上の自我に受け入れてやる、ということです。
嫌な記憶、嫌な自分、失敗、トラウマ、そういったものを受け入れ、乗り越えて、力にしていく。
そういうプロセスをもカウンセリングは内包しているのです。

カウンセリングの基本技法
じゃあ、内的な成長を促すために何をするか、ですけど。
カウンセラーの取りうる選択肢ってたくさんあるんです。
でも王道というか、基本は一つですね。
話を聴くこと、です。
アドバイスはあまり好んでしません。
内的な成長には、クライアントが自分で気づくことが何よりも重視されるからです。
言われてわかったつもり、これが最悪なんですね。
理想は、クライアントが自分で話しながら「あっ!」ってなる感じだそうです。
誰かに話をするという行為は、自分の中をある程度整理し、客観視することが必要です。
話しているうちに今までと違った見え方ができたり、視野が広がったりする経験は、みなさんあるのではないでしょうか。
カウンセラーは、クライアントの無意識の中を専門的知識と鋭い観察眼で想像し、適宜、クリティカルな質問を投げかけます。
その質問の答えを考えながら、またクライアントは自分の中を見つめ、ついには無意識の中にはびこっている心的事柄をとらえ、受け入れていくのです。
時間はかかりますが、カウンセラーは決して、こういうことじゃないんですか?というように答えを自ら口にしません。
クライアントに話し切らせる、それが良いカウンセラーの必須条件です。
客観視を促す壁として、また核心まで迫る伴走者として、カウンセラーは「話を聴く」に徹するのです。
質問の答え ~まとめに代えて~
カウンセリングって何なの?その目的は?
answer
・カウンセリングとは、クライアントとカウンセラーがルールの中でお互いに困難に立ち向かうこと
・具体的には、「話を聴く」ということ
・カウンセリングの目的は、クライアントにとっては外的な障害の解消。カウンセラーにとっては、クライアントの内的な成長とそれに伴う外的な障害の解消。
ちょっと難しい話になってしまったことを反省しています。
カウンセリングについては、これからガンガン書いていきます。
よろしくお願いします。
ではきょうはこの辺で。(^^♪
↓↓カウンセリングの全貌がわかる本です。超おススメ
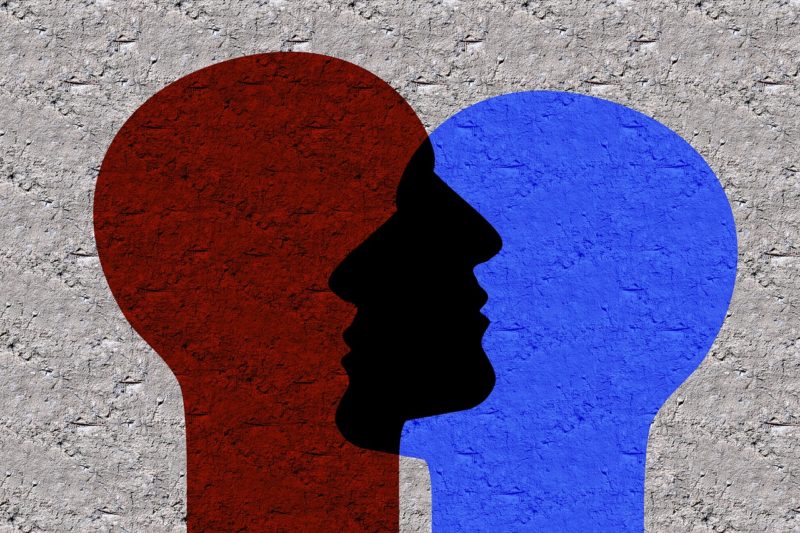




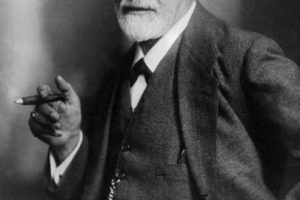






コメントを残す