Contents
言葉の力
中学校国語の教科書に大岡信氏の「言葉の力」というエッセイが収録されている。
僕はこの教材が好きだ。
概要は次のようである。
↓
着物を桜色に染めるとき使われるの材料は何か?正解は、桜の木の皮である。
多くの子どもは、桜色は桜の花びらから抽出されると考えているが、これは間違いである。
実は、桜の木は春、全身でピンクに染まろうとする。
目に見えるのは花びらのピンクだけだが、木の皮やそのずっと内部まで桜の木はピンク色の成分を蓄えている。
身をよじるように全身でピンク化していくソメイヨシノのダイナミズム。
桜の花びらのピンクは、桜が体全体で行う“ピンク化”という生命のダイナミズムのたった一部分でしかない。
桜の花びら一枚一枚のピンクは、桜の木全体の活動にその本質があるのだ。
同じことが言葉と人間の関係にも言える。
言葉の一つひとつは、花びらの一枚一枚だ。
言葉は、否応なくそれを発する人の“色”に塗られる。
一つの言葉は、その背後にいる人間の性格、経験、感情をはじめとするたくさんのものを内包せざるを得ない。
Aさんの言う「ありがとう」はAさんの色で染まっていて、Bさんの言う「ありがとう」はBさんの色で染まっている。
言葉の力とは、語彙の豊富さや文法の正しさを指すのではない。
言葉を発する人間の総合的な力こそ、言葉の力となりうる。
言葉の力を磨こうと思った時、自分という人間の成長を無視することはできないのだ。
とまぁ、ざっくりこんな内容。(僕の解釈も入っているけど)
玉置浩二のI love youはなぜ感動するのか?
話が大幅にそれるが、先日FNS歌謡祭を見た。
年々、見応えがなくなっていくな、と思いながら夕食を食べながら見ていた。
ふと、思った。
数年前まで玉置浩二がめちゃくちゃ出ていたのに、どこに行っちゃったんだろう?って。
森山直太朗と一緒に歌った『メロディ』や、槇原敬之との『田園』。
どれも素敵だったのに。
彼が双極性障害を持っていることをネットの記事で見たことがあったから、大丈夫なのかな、とも思った。
その夜、無性に彼の歌声が聞きたくなって、YouTubeを見て回った。
そこでたどり着いたのが『I love you』だった。
もちろん、尾崎豊の『I love you』だ。
玉置浩二のカバーを聴くのは初めてだったが、死ぬほど良かった。
泣きはしなかったが、ジーンとしてイヤフォンの中に余韻を求めた。
共感を得たくて、コメント欄をかたっぱしから読むと、実に多くの人が「感動した」「鳥肌がたった」という趣旨のことを書いていた。
1分もしないうちに、次の動画が流れ始めた。
そういう設定にしていたらしい。
画面の中で、今度はATSUSHIが同じ曲を歌っていた。
確かにうまい、文句ないほどうまい。
でも、心が動くことはなかった。
コメント欄には玉置verよりもたくさんのコメントが寄せられていた。
「うまい」「さすが」「マジで歌上手」「やっぱこの声最高」
歌手にとっての最高の誉め言葉が何なのか、僕にはわからない。
けれども、「感動した」というのは、それに近い称賛の言葉なんじゃないかな、とは思う。
なぜ、玉置浩二の歌には「感動」という言葉が贈られ、ATSUSHIには「うまい!」だったのか。
ボーっと考えていたら、言葉の力というものを思い出した。
尾崎の“色”
他人の曲をカバーする、というのは大変な作業だと思う。
曲には歌詞がある、言葉がある。
言葉には作り手である人間の“色”が宿る。
『I love you』は、作詞作曲共に尾崎本人だ。
その歌詞の一言一言には尾崎豊という人間全体が内包されている。
彼にとって、歌うことは生きることであったろうから、その曲には彼の何もかもが濃く深く入り込んでいる。
カバーをする歌手に与えられた選択肢は2つしかない。
つまり、
歌い手である自分の色で曲の中にある尾崎の色を上書きするか
自分の色をなるべく出さずに曲に宿る尾崎の色を邪魔しないか
である。
上書きする、とはその曲を自分の世界の中だけで理解しきり、その曲で自分を表現する、ということだ。
その曲について頭だけでなく心でも理解不能なところが一切なく、またその曲が自分を代弁してくれているという実感を持つ、とうことだ。
ただし、自分の色を上書きしようとしてうまくいくとは限らない。
いや、むしろその可能性の方が高いのだ。
その曲は自分から生まれたのではない。
その曲を自分の世界に完全に引き込むというのは、血の繋がっていない子どもを育てるようなものかもしれない。
僕の予想でしかないけど、玉置浩二は色の上書きに成功して、新しい創造を果たしたんじゃないかと思う。
実際、コメント欄には、「コピーじゃなく、増築だ!」といった意見も見受けられた。
対して、ATSUSHIの方は、自分を消して尾崎を尊重した感がある。
そこでは、オリジナル以上のものは生まれようがない。
再創造としてのカバー曲
こう考えてみると、感動を生むことのできるカバー曲は、再創造と呼べる。
一方で、それが成立する条件はかなり厳しいことがわかる。
まず、オリジナル曲の背後には誰がいるのかを考える必要がある。
尾崎のように伝説的なカリスマがもつ“色”を上書きできるのは普通の色ではない。
“色”は違えど、その鮮度は同じレベルでなければならない。
同じレベルの人間の総合力がないと、新たな創造は起こりえない。
オリジナルの人間の色が強ければ強いほど、その曲の色も強く、上書きは困難となる。
オリジナルの曲をカバー歌手が再創造するとき、問われるのはカバー歌手の人間としての総合力だ。
そういう目で音楽界を見たとき、このロジックはそんなに的を外してはいないと思う。
再創造か模倣かその目印は、そこに感動があるかないか、である。
ちなみに最近僕は、槇原敬之の「ファイト!」を聴いてすこぶる感動した。
是非聞いてみて欲しい。
では。







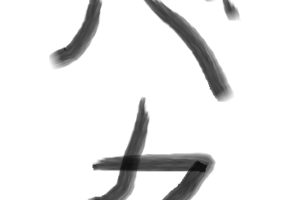



コメントさせて頂きます。
私は玉置さんとは2歳下。
ミーハー的な感想ではなく、尾崎豊はこの歌を歌い話題になった時期には私は30歳を超えていました。
ご本人が歌う「Ilove you」は歌詞も情感も素晴らしかった。
それから30年、玉置さんの「Ilove you」をYouTubeで聴いたときに本人が歌うものとは違った感動を
覚えました。(主さんの観たものとは違うと思いますが)
そもそも何故玉置さんがこの歌を歌おうとしたのか?
きっかけはともかく、今は亡き尾崎豊をリスペクトしていたからに違いないからです。
そして、玉置氏がソロ当時に担当していたのが尾崎氏と同じプロデューサー須藤晃さん。
同じ時代を生きた尾崎氏への鎮魂歌として、玉置氏は自分で咀嚼し気持ちを込めて歌ったのだと解釈しています。
コピーのようにメロディーラインを忠実に歌い、そこそこの歌唱力を持って歌っても正直感動はないと。
もちろんそれを望んでいる人はいるけど、玉置氏が尾崎氏の想いが重なった結果のカバーだと思います。
玉置氏は常々お客様に愛を伝え、想いを伝えようと歌っています。
それが、本家と違った表現になった部分も大きいのではないでしょうか。
結果的に情感を込めて歌う玉置氏の「Ilove you」は違いました。
今は削除されたYouTubeの再生回数は凄かった。
主がおっしゃるように「感動した」というコメントも多かったですが、「くずして歌うな」、「全然違う」
などと批判的なコメントもありました。
滅多に玉置氏は他者のカバーはしません。
唯一言えるのは尾崎豊への「贈り物」として自分の想いを込めた歌になったのでしょう。
もちろん玉置さんは意識はしていないでしょうが。
蛇足ですが、最初に歌ったのは玉置氏ご自身のコンサートで、ワンフレーズだけだったように聞いています。
あまりに反響が大きかったので、尾崎さんの奥様と息子さんに了解を得て初めてきちんと歌ったコンサートに
お二人をご招待したようですね。
カバーをする以上、そして今は星になった方のカバーをする以上、特別な情感を持って歌ったんだと思います。
玉置さんのセルフカバーではなく、本当の初カバーアルバム「群青の星」も今は亡くなった方々への鎮魂の意味
を込めたものだと言うことは想像に難くありません。
歌以外で話題になってしまった玉置さんですが、音楽や歌に対する情熱は半端ないと思います。
アーティストとしての玉置浩二の凄さを皆さんに分かって頂きたいと思うこの頃です。